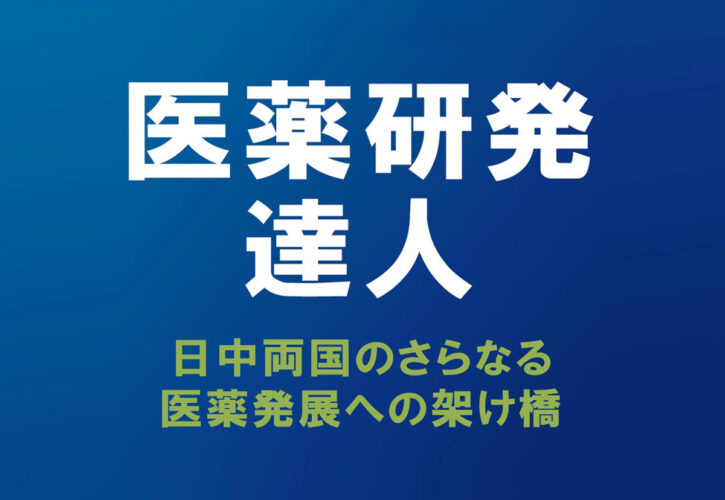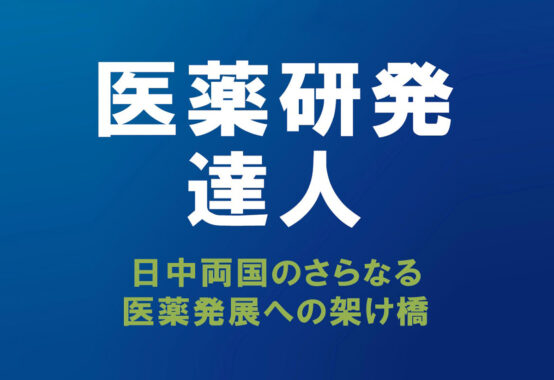第7回『研発客』臨床年次総会兼ChinaTrials15速報:日本の新規制が中国製薬企業の日本進出に与える影響
– ここ1, 2カ月でだいぶ盛り返した感のある中国製薬企業の日本進出熱
編集長コメント (2023年12月6日発行、第62号に寄せて)
今回の第62号では、2023年11月8-10日に上海で開催されたChinaTrials15の初日のワークショップに組み入れられた、研発客、医薬研発達人、Tigermedの共催による「中国の製薬企業向けの日本プロモーションセッション」である ” From IND to NDA: How To Implement the Clinical Development Plan in Japan” について取り上げた。
ChinaTrialsは、Lychee Groupによって2008年に創設された「中国における医薬品開発と治験」に焦点を当てた商業系最大のカンファレンスで、毎年11月、2015年の第8回までは北京で、2016年の第9回以降は上海で開催されている。なお、2020年はコロナ禍にて開催が無かったため、今回の2023年11月が第15回となっている。また、2021年の第13回以降は、Lychee Groupと研発客の共催となっている。
近年のChinaTrialsは約500名前後の参加規模であるが、特徴的なのは、中国製薬企業の経営層やグローバル製薬企業の中国R&D Executivesの登壇者が多いことと、プレゼンよりはラウンドテーブルに比重が置かれていることである。なお、DIA Chinaより規模は小さいが、ステージで話されている経営陣同士のほとんど本音の討論内容は奥が深いし、質疑応答の平均レベルも高い。
さらに、中国医薬創新促進会 (中国薬促会、China Pharmaceutical Innovation and Research Development Association, PhIRDA) 主催で、規模が巨大かつカバー範囲も広大な、中国医薬創新与投資大会 (China Biomed Innovation and Investment Conference, CBIIC) と比べると、より医薬品開発と治験に関連したセッションに絞られていることと、規模がこじんまりとしている分、ChinaTrialsでは登壇者と直接話す/知り合える/WeChat連絡先交換ができるチャンスが多いというメリットがある。
[参考: 医薬研発達人第12号(2021年12月6日発行)「第6回中国医薬創新投資大会(CBIIC):導入(Buy)、フォロー(Follow)、改良(Improve)から真のイノベーションへ」、医薬研発達人第47号(2023年4月24日発行)「2022 CBIICにて中国医薬品規制改革の成功の軌跡と今後の課題を見る」]
医薬研発達人が中国で日本プロモーションセッションを行うのは、6月18日の蘇州での第15回DIA中国年会Day 3に次いで今年2回目であるが、前回6月のフロアと違って、今回11月のフロアでは、聴衆からの大きな熱量と真剣さを感じた。
[参考: 医薬研発達人第51号(2023年7月3日発行)「第15回DIA中国年会報告(第一弾)中国バイオテク企業が日本へ進出するということ」、医薬研発達人第52号(2023年7月17日発行)「第15回DIA中国年会報告(第二弾) 医薬研発達人創刊2周年記念号」]
すなわち、具体的かつ的を射た質問の数々からも、今回11月のフロアでは、聴衆が「日本市場進出や日本での治験実施」に明らかに興味を持っていて、実際よく勉強しているように感じた。
その理由として、今年6月から11月までの5か月間の変化を振り返ると、日中両国政府の関係が少し改善した、中国の経済減速がより顕在化してきた、長引く円安、コロナ禍からの回復状況の持続などが挙げられるが、今年11月のChinaTrials15の中国人参加者 (ちなみにChinaTrials15では3日間を通じて自分以外には一人の日本人も見かけなかった) と話していて圧倒的に感じたのは、「今年6月9日に厚労省から出された有識者検討会報告書」や「今年7月や9月の薬事検討会結果」に代表される「ドラッグロス・ドラッグラグを解消するために大胆な規制緩和もいとわず真剣に立ち向かう日本国や日本政府の本気度」を中国の産業界が肌で感じ取り、これからは日本に大いにビジネスチャンスあり、と捉えていることである。
そのことがChinaTrials15以降の中国産業界の動きにも早速表れている。
先週、11月28日から3日間、PhIRDAの日本訪問団が15社30名に迫る規模で東京(&神奈川)にやってきた。主目的は、日本でのパートナー探しで、錚々たる面々が中国各地から同時に来日し東京に集結した。
私は、PhIRDAの支援者兼日中医薬品開発専門家として、初日に彼らにプレゼンを行ったほか、製薬協との会議、医療機関訪問等をサポートするなど、彼らに3日間帯同した。
このPhIRDAの日本訪問は、完全クローズの非公開イベントなので、本来、医薬研発達人には何も書くことができないが、昨日12月5日にPhIRDA自身が、WeChatで、先週の日本訪問報告を行い、公開情報となったので、今、こうして医薬研発達人でも本イベントについて記述することが可能となった。本62号の発行日が2日遅れの12/6(水)となったのは、このような事情によるものなので、お許しいただきたい。
このWeChatで公開されたPhIRDAの日本訪問報告は、製薬協や製薬企業での集合写真のほか、いつどこで誰とどんな行事を行ったのか、相当細かく書かれているので、中国語表記ではあるものの、一度ご覧になることをお勧めする。
中国药促会代表团到访日本制药工业协会及武田制药(2023年12月5日、PhIRDA発行)
https://mp.weixin.qq.com/s/mxeMXkHEUv3r3fGdNJh7iQ?poc_token=HMRhcGWj020l6bjpwHASxFEw9fqEu7o25e6MX6yj
今回のPhIRDA日本訪問団の熱量はハンパなく、本当に火傷しそうになるくらい熱かった。6月のDIA中国年会の頃とは全く比較にならず、11月上旬のChinaTrials15の時よりも格段にヒートアップしていた。
来年、医薬品開発/ビジネス周辺の日中連携は、産業界をドライバーとして大いに前進することを確信した。
高野 哲臣(t2T Healthcare株式会社代表取締役社長)
続きは、以下のリンク先をご参照ください。
https://mp.weixin.qq.com/s/9_aeNbCUAGpHvIWnJjTjRg