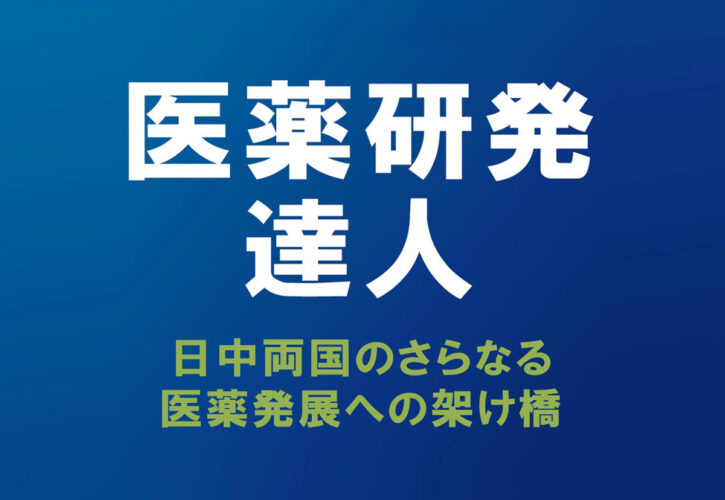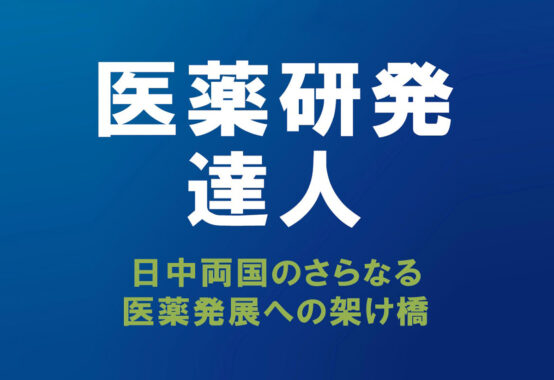なぜ香港は新たな医薬品医療機器規制当局を設立するとともに、ICHに参加するのか?
– 先月香港で日本企業にも大きな影響のあるCPP規制緩和開始!
編集長コメント (2023年12月18日発行、第63号に寄せて)
今回の第63号では、「2023年11月1日から開始済の『新薬承認における1+ mechanism』に関する 2023年10月26日の香港特別行政区政府Press Release」、ならびにその翌週10月31日にチェコ・プラハでのICH総会で承認された「香港規制当局のICHオブザーバー入り」について取り上げる。
まず、前者についてだが、1+ mechanism開始に関する10/26の香港政府発表は、中国の製薬企業から非常に好意的かつ好機と捉えられている。
一方、この大きなニュースを日本であまり聞かないのは、日本側における興味, 感度, 理解の低さ and/or 実際の対象ケースの少なさに起因しているように感じられる。
なにはともあれ、その10/26 Press Releaseの実物を見ていただきたい。
「1+」新药审批机制将于十一月一日生效 (2023年10月26日(星期四))
https://sc.isd.gov.hk/TuniS/www.info.gov.hk/gia/general/202310/26/P2023102600379.htm?fontSize=1
“1+” mechanism for approval of new drugs to commence on November 1 (Thu, Oct 26, 2023)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202310/26/P2023102600381.htm?fontSize=1
このPress Releaseには、「重篤疾患(がんなど) あるいは希少疾患を治療する新薬(香港における新薬の定義は中国とは異なり新有効成分) の場合、1 CPP (Certificate of a Pharmaceutical Product, 製剤証明書) + 当地/現地 (中国語では”本地”) の臨床データにて、香港NDA承認可。この新規制は2023/11/1から施行する」と書かれている。
香港における化学薬品/生物製剤新有効成分のNDA申請ガイダンス (Guidance Notes on Registration of Pharmaceutical Products Containing a New Chemical or Biological Entity, Version November 2023) (https://www.ppbhk.org.hk/eng/files/Guidance_on_Reg_of_Pharm_Prod_Containing_New_Chem_or_Bio_Entity_en.pdf?v=2ykund) では、10/26 Press Releaseの記載がまだ反映されておらず、2 or more CPP requirementの話しか載っていないが、今回の第63号の本文中の表のステップ1にも明記されているように、この1+ mechanismは、実際のところ、既に11/1から実装されている。
[補足:2022年11月のガイダンス改定によってブラジル、中国、韓国、シンガポールの4カ国が香港のCPP参照国に追加されたものの、「それら4か国のみのCPPsでは不可」と、従来からの32参照国とは扱いに差があったが、2023年11月の改定時には、その差がなくなり、36参照国の扱いが一律になった]
この当地/現地 (中国語では”本地”) の定義に関してはどこにも記載が無いが、香港のみならず中国大陸も含まれるだろう、と私は見立てている。
読者の皆さまの中で、「日米欧のいずれかで承認済(1 CPP有) の重篤疾患(がんなど) あるいは希少疾患治療の新薬(新有効成分) にて、香港(あるいは中国) の臨床データをお持ちの方は、11/1以降、香港でNDA承認される道が開けているので、香港での申請→承認→上市を前向きに検討されてはいかがだろうか。
なお、今回の第63号の本文中に幾度か登場する “Primary Evaluation” という用語の定義に関しては、「行政長官2023年施政報告」(The Chief Executive’s 2023 Policy Address) (https://www.policyaddress.gov.hk/2023/en/p139a.html) の中で、 “to directly approve applications for registration of drugs and medical devices based on clinical data, without relying on other drug regulatory authorities” と明記されている。
次いで、後者についてだが、香港衛生署 (Department of Health) 内の規管事務 (Regulatory Affairs) の組織の中で、薬物弁公室 (Drug Office) と香港薬剤業及毒薬管理局 (Pharmacy and Poisons Board of Hong Kong, PPBHK) は上下の関係ではなく、横並びの関係にあるが、10/31のICH総会で、ICHオブザーバー入りが承認された香港規制当局は、香港薬剤業及毒薬管理局 (Pharmacy and Poisons Board of Hong Kong, PPBHK) の方である。
すなわち、2024年以降に設立予定の「香港医薬品・医療機器監督管理センター」 (香港薬物及医療器械監督管理中心, Hong Kong Centre for Medical Products Regulation, CMPR) は、まずはPPBHK傘下に設立されて、その後、独立機関として昇格するものと思われる。
最後に、NMPAとCMPRの相互認証について私見を述べる。
まず、想像に難くないが、「中国NMPA承認を参照とした香港CMPR承認」の道は、比較的容易と思われる。今回の11/1からの香港における規制緩和は、主として中国の製薬企業をターゲットにしたものと映るが、中国大陸発の1 CPP新薬を香港市民に速やかに届けようとする、北京の合意を得た、香港政府の施策であり、この規制緩和によって恩恵を受けるのは、中国の製薬企業と香港市民の両方である。
一方、「香港CMPR承認を参照とした中国NMPA承認」の道は、導入開始まで、まだまだ何年も掛かるであろうし、たとえ導入開始された後であっても、この道は相当険しいだろうと予想する。
まず大前提として、新設規制当局である香港CMPRの審査能力が中国CDEに追い付いてくる必要がある。さらに、今後も引き続き、最も大きな課題と考えられるのは、現地臨床データのrequirementである。人口750万前後の香港と人口14億の中国大陸とでは、承認要件となる現地臨床データのrequirementが大きく異なることは容易に予想される。
中国CDEによる香港承認に伴う中国大陸での臨床データ減免は、可能性はゼロでないと思うが、香港上市後、何年も経て、十分な市販後臨床データが集積されない限り、ほぼほぼ望めないのでは、と推察される。
日(米欧)の製薬企業の中には、中国を避け、まずは香港で承認取得して、それを機に、中国で承認取得できたら、と考える人々がいるかもしれないが、香港経由でなく、最初から中国に直接行く方が、今後も引き続き、ずっと早くて遥かに確実であろうと考えている。
【年末のご挨拶】
おかげさまで、医薬研発達人は、今年、2023年1月4日発行の第39号から、本日12月18日発行の第63号まで、隔週の月曜発行をほぼ維持し、計25回発行することが出来ました。読者の皆さまの日頃のご愛読に心より感謝申し上げます。
次号第64号は、突発的な事象が発生しない限り、2024年1月4日(木)に発行予定です。来年も引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。
どうぞ良い新年をお迎えください。
高野 哲臣(t2T Healthcare株式会社代表取締役社長)
続きは、以下のリンク先をご参照ください。
https://mp.weixin.qq.com/s/2PyEXi-aoQr0-ODNJf7iVQ