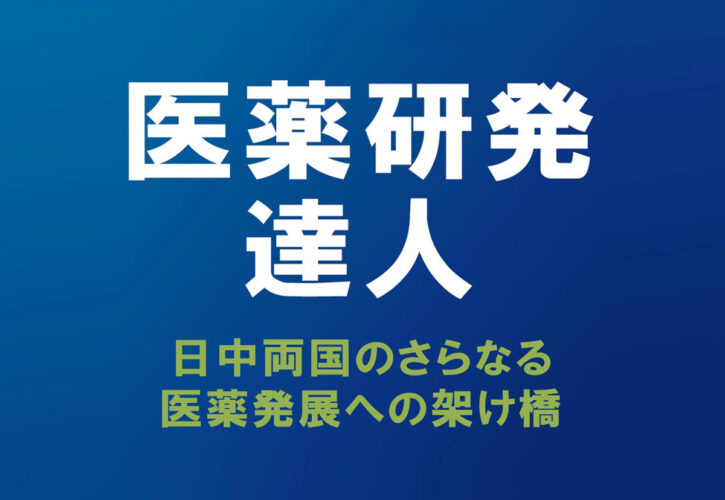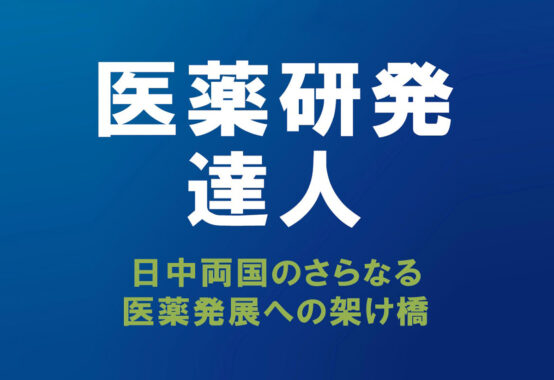2023年国家医療保険談判(薬価交渉)結果発表: 創新薬が迎えた新たなチャンス
– 中国の新薬薬価抑制策に明るい兆しが見えてきた!
編集長コメント (2024年3月11日発行、第69号に寄せて)
突然の案内でたいへん恐縮ですが、今回の医薬研発達人第69号は、休刊前の最終号となります。詳細は、本コメント欄の後半で述べさせていただきます。
=============================================================
今号第69号の医薬研発達人では、第17-18号(2022年2月21日ならびに3月7日発行)「中国の医療保険制度と薬価交渉の概観」、第46号(2023年4月10日発行)「2023年度中国国家医療保険償還医薬品リスト(NRDL)交渉結果」に引き続き、2023 年7月の製薬企業による申請資料提出から11月までの談判等を経て2023年12月13日に国家医療保障局 (National Healthcare Security Administration, NHSA) から発表された2023年国家医療保険償還医薬品リスト (National Reimbursement Drug List, NRDL) について取り上げる。
| NHSAとNRDLに関する号と発行日 | タイトル | 内容 |
| 第17, 18号 (2022年2月21日ならびに3月7日発行) | 中国の医療保険制度と薬価交渉の概観 | 国家医療保障局 (National Healthcare Security Administration, NHSA) の歴史、国家医療保険償還医薬品リスト (National Reimbursement Drug List, NRDL) のプロセス、2021年11月に行われた談判の緊迫した状況など |
| 第46号 (2023年4月10日発行) | 2023年度中国国家医療保険償還医薬品リスト(NRDL)交渉結果 | COVID-19の感染者急増により1カ月遅れで2023年1月に終了し2023年3月1日から保険償還が開始された前回2022年談判の結果 |
| 第69号 (2024年3月11日発行) | 2023年国家医療保険談判(薬価交渉)結果発表: 創新薬が迎えた新たなチャンス | 今号の本文参照 |
これら3回にわたる号を見比べると、すぐに気付くが、新薬の談判における雰囲気や勝手や情勢は、2021年末→2023年初→2023年末の3年間で、大きく変化している。
まさしく、約1年前の第46号の編集長コメントで、
「⽇本においては、2022年8⽉の発⾜以来、2023年4⽉4⽇までに「医薬品の迅速·安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」が既に1+11回開催されている。中国においても、薬価制度等に関して、sustainabilityを合⾔葉に、部⾨横断的な⼤幅な軌道修正が、今こそ求められているのかもしれない。」
と述べたが、実際、中国政府は、その後、既に大幅な軌道修正を開始している。
談判による平均薬価値下げ率は2021年(61.7%)→2022年(60.1%)→2023年(61.7%)と相変わらずの厳しさで、談判の交渉成功率も2021年(80.3%)→2022年(82.3%)→2023年(84.6%)と年々わずかな向上が得られているに過ぎないが、多くの事例が本文に記載されているとおり、こと創新薬(と希少疾患治療薬)に関しては、国産薬のみならず外国からの輸入薬が中国から離れていくことのないように(中国パッシングによって中国のドラッグロスが進むことのないように)、次から次へと打ち手を講じている。
薬価に関する懐事情は厳しく、決して余裕があるわけではないものの、創新薬/希少疾患治療薬/必要性の高い薬剤とそうでない薬剤とで対応に差をつけることによって、うまくバランスを取って、sustainableを実現しようとしている。
2024年1月22日の中国共産党中央弁公庁と国務院弁公庁による「浦東新区総合改革試行実施方案(2023-2027年)」も、2月5日のNHSAによる「新規上市化学薬品の第一次価格形成メカニズムの構築による高品質イノベーションの奨励に関する通知」(パブコメ)も、そういった考え方の延長線上にある。
ひとつひとつの政策が実によく考えられているなど、中国から学ぶことは、本当に多い。
=============================================================
さて、冒頭で述べたとおり、この度、のっぴきならない事情により、今号第69号を以て、医薬研発達人を休刊することになりました。
日本も中国も、現在、医薬品開発を取り巻く規制改革や環境改善が急ピッチで進められており、両国はお互いに学ぶことも多いので、読者の皆さまにお伝えしたいことは、まだまだ沢山あるのですが、やむを得ない状況となってしまいました。
おまけとして、休刊前の誌面をお借りして、先週の日中関連のhot topicsに触れさせていただきます。
日本では、有識者検討会(医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会、2022年9月~)に端を発し、その後、薬事検討会(創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会、2023年7月~)や構想会議(創薬力の向上により国民に最新の医薬品を迅速に届けるための構想会議、2023年12月~)等々、規制改革・環境改善に向けた情報収集や分析、建設的な議論や実効性のある提案が続いています。
その中で、新しいところでは、先週3月7日(木)に開催された内閣府の規制改革推進会議の第7回健康・医療・介護ワーキンググループオンライン会議において、R&D Head Clubが発表した「日本のIRBの課題と日本でのSingle IRB実現に向けた国を挙げての取り組みの必要性」について、河野太郎行政改革担当大臣がビデオメッセージの中で特段に取り上げて後押しするとともに、大阪大学もその方向性を支持する場面がありました。長年にわたるR&D Head Clubや製薬協、PhRMA、EFPIA等の地道な活動が、アカデミアや省庁をまたぐ国の組織にようやく認められ、実を結びつつあるわけで、本当に嬉しく思います。今後は、是非ともこの流れを一気に加速させて、一日も早く、日本でもSingle IRBが実現されることを願っています。
(https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240307/medical07_agenda.html)(https://www.youtube.com/watch?v=jylOGXjr7aY&t=406s)
一方、中国に関しては、2015年の少し前から規制改革が継続して大胆かつspeedyに進行中ですが、Boston Consulting Groupの柳本岳史氏が同じく3月7日に開催された第3回構想会議で述べているように、「今や新規モダリティ全体でも4割の開発パイプラインを占める中国発」と、それを生み出している中国の「後追い戦略」には、我々も大いに学ぶ余地があります。(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/souyakuryoku/dai3/gijisidai.html)
日中両国は、今、変化がとても激しいため、日々勉強を続けていないと、あっと言う間に、置いてけぼりを食ってしまいます。
医薬研発達人は、2021年7月5日発行の創刊号以来、隔週月曜発行をほぼ維持して、2年8カ月の間に第69号まで発行することができました。皆さまには、これまで長い時間、お付き合いをいただき、誠にありがとうございました。心より感謝申し上げます。
いつ再開できるのか、どんな形で再開できるのか、現時点では分かりませんが、できるだけ早く、なんとか次号の発行に漕ぎ着けて、皆さまにまた誌面でお会いできたらと考えています。
どうぞお元気で。
高野 哲臣(t2T Healthcare株式会社代表取締役社長、連絡先: t2.takano@t2thc.com)
続きは、以下のリンク先をご参照ください。
https://mp.weixin.qq.com/s/axDR54i4fF3_ZAHwt-97hA